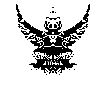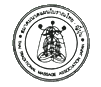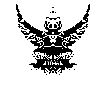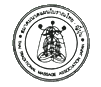■先史時代
東南アジアでの人類の居住は、50万年以上遡ります。最近の考古学の研究によると、 紀元前 4000年までには、現在のタイの土地に初期の青銅器文明の中心地としてコミュニティーが出現したとされています。この発展によって、水稲の耕作に伴って、社会的政治的な組織構成が進みました。タイから中国も含むアジア全域までこれらの革新が伝わった可能性を示唆する研究もあります。 マレー人 、 モン族 および クメール人の文明が繁栄していました。現在この地に住むタイ人は、中国南部起源の民族と言語的に関係があり、 6世紀 ~ 7世紀に、中国南部から東南アジアへと移住した可能性が大きいとされています。 |
| |
 |
| |
| ■ アンコール王朝(クメール王朝) |
| |
| 現在の東南アジアにあった王国で、現在のカンボジアの元となった国。これより以前にあった チェンラ王国の流れを受け継ぐ王国で、その勢力が最大化したときは、現在のタイ東北部 、ラオス 、およびヴェトナムのそれぞれの一部をも領有していました。アンコール遺跡をはじめとする、一連のクメール遺跡などはこの王朝による建造物で、アンコール・トム (ノーコー・トム)を首都としていました。宗教的には、13世紀 に上座部仏教がインドシナを掌握するまで、ヒンドゥー教や大乗仏教 の混じった宗教が信仰されていました。 アンコール王朝時代の医学は、薬用植物から作ったと考えられる薬や仏像を使った呪文や祈祷によって治療が行われていたことが碑文からわかっています。 |
|
|
| |
 |
| |
| ■スコータイ王朝 |
| |
現在のタイ人は、自分たちの国家の設立を13世紀としています。伝承によると、1238年、タイ民族の指導者がスコータイでクメールの大君主を倒し、タイ王国を設立したとされています。その王国の衰退の後、 1350年に新しいタイの王国がチャオプラヤー川 沿いに成立しました。スコータイ王国と時を同じくしてタイ北部の チエンマイ から中国のシップソーンパンナーにかけて ラーンナータイ王国 が繁栄しました。
中国南部の雲南から南下してきたタイ族は、 13世紀ごろまでは強力なアンコール王朝の支配力の下にありました。ところが、アンコール王朝のジャヤーヴァルマン7世が崩御すると、タイ人が進出していた地域におけるアンコール王朝の支配力が次第に弱まり始めました。ラート(現在のペッチャブーン市)の小タイ族領主の ポークン・パームアンと、バーンヤーン(現在のナコーンタイ郡)の小タイ族領主の ポークン・バーンクラーンハーオ が共同でクメール人の勢力を追い出し、当時アンコール王朝の主要都市であったスコータイに小タイ族の王朝を建て、バーンクラーンハーオが王位に就き シーインタラーティット と称したのです(スコータイ王朝の成立)。ちなみにパームアンはそのとき摂政位に就いたと伝えられています。 |
| |
| スコータイ王朝は三代目ラームカムヘーン大王時代には黄金期を迎えました。パヤオ王国のガムムアン王、 ラーンナータイ王朝 のマンラーイ王と同名を結び、マレー半島全域から、ベンガル半島までを掌握しました。 ラームカムヘーン王は最初のタイ文字を定め、中国との貿易も行い、陶磁器製造技術を持ち込みました。 ラームカムへーン王の碑文には、「国民が病の時に利用できるように、カオルアン山とカオサッパヤー山に薬用植物園をお作りになった。」とあります。その山はスコータイ県のキリマート郡に現存しています。また、碑文には、「水に魚あり、田に稲あり、王は民に税を課さず、他人の富を欲しがらない~王宮の門には鐘が吊るされ、民が争いごとを起こしたときには、その鐘を鳴らすが良い、王はその訴えを聞き公平に裁くであろう。」とも記されており、当時の豊かさをうかがい知ることができます。 |
|
|
| |
しかし ルータイ王時代までには各地で離反が相次小国になり、後に王位に就いたリタイ王はすでに仏法の研究を積極的に行い、三界論を著して、民衆の仏教理解を深めさせました。同時にタイ史上初めての一時的な仏教出家を果たし、これはすでに没落の兆候を示していたスコータイ王朝をリタイが仏法を持ってつなぎ止めようとしたことにあるとされています。リタイは結果的に王権思想の一つタンマラーチャー(ダルマラージャ)の思想を確立したのです。
当時の教育や文化の中心的役割は、テラワーダ仏教の寺院が担っていました。寺院の僧侶は薬用植物についても知識を持ち、庶民に薬用植物を使った治療をアドバイスしていたと考えられています。
このあたりでアユタヤ王朝 が台頭します。アユタヤ初代王・ ラーマーティボーディー1世 はスコータイ王朝に圧迫を加え始めたが、ラーマーティボーディーはスコータイを掌握することはしませんでした。サイルータイ王の時代にはパングワ王によって国を分離させられ、スコータイ王家はピッサヌローク を治めるのみになりました。その後細々と国は続いていましたが、マハータンマラーチャー4世 の時代に、跡継ぎが断絶し、スコータイ王家の親戚であったアユタヤ王朝のラーメースワン王子(後のボーロマトライローカナート王)が後を取る形で、アユタヤ王朝に吸収され、スコータイ王朝は消滅しました。 |
| |
 |
| |
■アユタヤ王朝
アユタヤ王朝 (1351年 - 1767年)は現タイ の中部を中心に展開したタイ族 による王朝。創設者はラーマーティボディー1世(ウートーン王)。 |
| |
| タイに起こった各時代の王朝同様、中国とインド、ヨーロッパ方面を結ぶ中間に位置する地の利を生かし、貿易が国の富として重要でした。アユタヤ王朝でも王家を中心として、独占的な貿易が行われました。主に中国への米の輸出で国力を付けたほか、日本、琉球などの東アジア国家、東南アジア島嶼部、アラブ・ペルシア方面や西洋と活発に貿易を行い、莫大な富を蓄えました。この富を背景にアユタヤでは当時繁栄していたクメール文化を吸収しつつ、中国、ヨーロッパ、ペルシャなどの文化の影響を受けた独自の華やかな文化が開花しました。 |
|
|
| |
ウートーン王の出身については、歴史資料上はっきりしていません。そのためいくつかの説が提出されてきました。なかには、疫病(おそらくは コレラ )で見捨てたチエンセーンから移住してきたといった説や、スパンブリー出身、 ロッブリー出身説などがあります。いずれにしろ、アユタヤ朝創設当時の、近隣の状況は、北にスコータイ朝 が隣接していたにもかかわらず、アユタヤを創設したタイ中部は、スコータイ朝の領土でなかったこと、さらに、アユタヤ時代が始まる直前までの古い遺跡がタイ中部で見つかっていることから、歴史資料としてまだ見つかっていない王朝がすでに存在していたことが窺えます。あるいは、小国が並立していたというようなことも考えられます。例えば、この空白期(アユタヤ朝創設以前のタイ中部)にロッブリーやペッチャブリーはスコータイ朝とは別に中国に朝貢しています。したがって、ウートーン王の出身もおそらくタイ中部のある国の王家からだと考えるのが妥当であろうと考えられています。ちなみに、ウートーンというのは金のゆりかごを意味し、伝承の中でタイ中部でこの名を持つ王は多い。つまり、タイ中部の名づけの習慣でもあります。
ウートーン王は、王朝年代記ではラーマーティボーディーというなで記述されています。王が即位するにあたり、スパンナプーム王家(スパンブリー)の協力が不可欠であったことは、後の対スコータイ政策で顕著となります。
ラーマーティボーディー(1世)は国内統一のため、セイロンから仏僧を招いて 上座部仏教 (小乗仏教)を国家の公式な宗教とするとともに、ヒンドゥーの法典である ダルマシャスートラ やタイでの慣習を元に(三印法典)を整備しました。この三印法典は近代的な法典が整備される 19世紀 までタイの基本法典として機能することになります。
14世紀末までにはアユタヤ王朝は東南アジア最大の勢力として見なされるようになりますが、完全に東南アジア地域を圧倒するほどの人口に欠けていました。このため、当時衰退しつつあったクメール王朝へ勢力を伸ばしつつあったベトナム勢力に対抗するため、ラーマーティボーディーは晩年 アンコール (クメール人の都市)を攻撃しアユタヤの図版に加えました( 1362年 )。しかし、アユタヤはアンコールの完全な掌握を遂行することはできず、スコータイ王国との関係は、スコータイがアユタヤに朝貢する形となりましたが、その後、100年かかって、アユタヤ朝がスコータイ朝を併合し、スコータイ朝は消滅することになります。しかしこの過程で、アユタヤに新たに興ったスパンナプーム王家とスコータイの王家との姻戚関係が強くなり、その後もスコータイ王家は存続したと考えられます。
諸国との貿易も盛んで中国人、マレー人、ポルトガル人、そして日本人町などの居住区が存在していました。日本人町には、800~3000人の日本人がいたと言われていますが、1603年から1635年までの鎖国が始まるまでの32年間で、徳川幕府は御朱印船で55回も渡航し、タイとの貿易を進めました。山田長政が日本人義勇隊長として活躍したのは有名な話です。アユタヤ王朝の医学は、仏教哲学に沿ったものから呪術や占星術に至るさまざまなものが混在していたと考えられています。そしてさまざまな知識が区分けされました。医学の分野では、マッサージ医師であるモーヌアッド局、薬剤師、小児科医、王家の医師であるモールアンなどがあったようです。
1659年~1661年までのナライ王が統治をした期間には、色々な国の医師による医学書がまとめられ、王に献上されました。「ナライ王の医学書」と呼ばれていますが、ここには81種類の薬の処方が書かれており、庶民のために薬用植物を売る店も多く存在していました。当時のフランス政府渉外官であったラ・ルベールは、次のように報告をしています。「タイ人は病気になっても何もせず、ただマッサージをするだけである。そしてたいていの場合治ってしまう。」この言葉から、タイの伝統医学の中でもタイマッサージが広く普及していたことがうかがえます。宮廷でも医療の一環として行われていたようで、アユタヤ朝時代の文献「ナライ王の医学書」には、マッサージが宮廷で治療法として用いられたことが記録されています。宮廷の中にはマッサージ師という職位があり、比較的高い地位であったようです。
15世紀 にはマレー半島のマラッカ王国がアユタヤの悩みの種となります。マレー半島ではマラッカやタンブラリンガ以南のマレー半島諸都市が15世紀早くからイスラム教に改宗するようになり、独立を宣言するようになったためです。結果的にアユタヤはマレー半島南部を失いますが、マレー半島北部を維持し高級品を求めてやってきた中国出身の商人により国内の経済は潤うことになります。
一方、西のビルマは地域の覇権を競い、16世紀ごろから執拗にアユタヤを攻撃を繰り返しており、アユタヤはこれに頭を悩まされることになります。ビルマのタウングー王朝 の君主、 バインナウンは 1569年にアユタヤ王、マヒントラーティラートを下していますが、ナレースワン によってアユタヤは再興されました。この後、ビルマが内乱に見舞われたことから一時ビルマの侵攻は収まったように思われましたが、コンバウン王朝が興ってから再びアユタヤはビルマの侵略に悩まされます。 1767年にはシンビューシンによって アユタヤ王朝 が滅亡します。このときアユタヤの町は徹底的に破壊されていたため、ビルマ軍が退却した後、新たに王となったタークシンはアユタヤ再興をあきらめ トンブリーへと遷都します。 |
| |
 |
| |
■チャクリー王朝 ラーマ1世
正式名称:プッタヨートファーチュラーローク王
別名・通称:チュラーローク王 |
| |
| ラーマ1世 (Rama I、 1737年3月20日 - 1809年9月7日)は タイ王国 の現王朝、 チャクリー王朝 の創始者。幼名は トーン・ドゥワン 。アユタヤ王家の血を引いており、アユタヤー時代の士官、 チャオプラヤー・コーサーパーンの子孫と言われています。アユタヤー王朝末期にすでに官吏として士官しておりルワンヨック・クラバットの爵位名も持っていました。ラーマ1世の称号は ラーマ6世 によって制定されたもの。 |
|
|
| |
彼の仕えたアユタヤー王朝が後に、1767年 (タイ仏暦2310年)にビルマ(現ミャンマー) に占領されると、翌年に 華人勢力のタークシンがビルマ兵を駆逐し、トンブリー王朝 を起こしタイの王に就きますが、このとき ルワンヨック・クラバット (ラーマ1世)はタークシン王に仕えました。ルワン・ヨッククラバットは、タークシンがラヨーンで挙兵したときにタークシンの母を保護のためラヨーンに送り届けた手柄でプラ・ラーチャワリンに昇進したのをはじめ、多くの戦果を上げ、プラヤー・アパイロンリット、プラヤー・ヨマラート、チャオプラヤー・チャックリー、ソムデットチャオプラヤー・マハーカサットスックへと次々に昇進していったため、猛将としても知られています。
トンブリー王朝のタークシン王は晩年に精神錯乱状態をきた時、 チャオプラヤー (ラーマ1世)は国内の混乱をおそれて、カンボジア遠征を中断し、トンブリーに戻り、タークシン王を処刑しました。この後、チャオプラヤーは王に就くが、タイの正史ではチャオプラヤーは民衆に推挙され王になったということになっています。王になったため名前を プラバートソムデットプラ・プッタヨートファーチュラーローク 、世界最上の天上の御仏の意)と名乗りトンブリーから チャオプラヤー川 を挟んで対岸である東岸にバンコク (正しくはクルンテープ)を建設し遷都した後、チャックリー王朝を創設し、アユタヤー王朝の神権政治を継承しました。
チュラーローク王(ラーマ1世)は、即位後も猛将ぶりを発揮し、数回に及び進軍してきたビルマを駆逐し、国内を安定させました。国内が安定してくると、『三印法』を整備し官制度を整備しました。またアユタヤー王朝の末裔であることを見せるため、多数の学者を導入してビルマ占領時代に散逸した文学 ラーマキエン 、イナオ を再編集しました。今でもラーマ1世版のラーマキエンは数あるラーマキエンの中でも秀逸な作品として知られています。観光地と知られる ワット・プラケーオ (エメラルド仏寺院)も彼の建設によるものです。ここにチュラーローク王は ヴィエンチャンから奪ったエメラルドのブッダを設置しました。彼はこの他数多くの寺院を建てたとされています。彼の名を冠した有名なものとしてチャオプラヤー川 に架かった最初の大橋、サパーン・プットなどがあります。また、アユタヤ王朝時代に創建されたといわれるバンコク最古の寺院ワットポーの本堂を修復し、ワット・プラチェートゥポン・ウイモンマンクラワートと新たな名前をつけました。
1788年(タイ仏暦2331年)には、薬用植物の手引書を編纂し、ワットポー境内にルーシーダットンの彫像を作りました。実際にいくつ作られたかは定かではありませんが、当時は粘土に金箔を貼ったもので、耐久性に欠けており、後に作り直されることとなります。
この時代には、アユタヤ王朝時代と同じように、モーヌアッド局が置かれ、王家の医師であるモールアンと庶民の医師であるモーラーサドーンに分かれていました。また当時、一般庶民も医学書を作るようになり、医学的な知識が一般庶民の間にも広まっていったことがうかがい知ることができます。 |
| |
 |
| |
■チャクリー王朝 ラーマ2世
正式名称:プッタルートラーナパーライ王
別名・通称:
ナパーライ王 、 ルートナパーライ王 |
| |
| ラーマ2世 (Rama II、 1766年 2月26日 - 1824年 7月21日 )は タイ王国 の チャクリー王朝 の第2代目の王で、ラーマ1世の息子。幼名チム。チムは 1782年 (タイ仏暦 2345年)ラーマ1世が即位すると クロムルワンイッサラスントーン王子の名を戴きました。その後 タイの仏教 の伝統に則って出家しました。 1806年 (タイ仏暦 2349年)の副王の死によって自分が副王になり、皇太子となりました。 1809年 (タイ仏暦 2352年)にラーマ1世が崩御したので王に即位。治世の前半はたびたび ビルマが攻めてきたが、後半ではビルマがイギリスに占領され、攻めてこなっくなったため、国内の整備などを行いました。タイの文豪の一人にも数えられる詩人で、文学面での功績は大きい。ブンナーク家などの貴族に内政を任せっぱなしにしていたので、政治的にはあまり実権を持たなかったようです。 |
|
|
| |
 |
| |
| ■チャクリー王朝 ラーマ3世 |
| |
ラーマ3世は、父であるラーマ2世譲りの詩人で、叙事詩『 クン・チャーン=クン・ペーン 』の作詩にも関わりました。また、ラーマ3世の治世には戦乱が減ったため世の中の安定によってインフラの整備を精力的に行うことができました。そのためラーマ3世までを「チャクリー王朝の建設期」とされています。
なお正式名称の一部である ナンクラオ の名称はラーマ4世による諡号であって、生存中に一般的に用いられた正式名称(の一部)は チェーサダーボーディン。彼はラーマ3世はラーマ1世の統治下、その初孫としてバンコクの王宮に生まれました。幼名は タップ 。父親はイッサラスントーン親王(後のラーマ2世)で母親はリアム(後のクロムソムデットプラ・スラーライ)。 |
|
|
| |
物心つく頃から祖父と父親に連れられ戦場につれられており、帝王学などはこのなかで身につけていったと考えれています。のちにラーマ1世が崩御し父親ののイッサラスントーンが王位につくと、タークシンの息子であるカサットラーヌチット親王が反乱を起こします。このときタップ親王はカサットラーヌチット親王を討伐する役を与えられ成功します。このとき、クロムムアン・チェーサダーボーディンという官名をもらっています。
タップ親王37才の時にラーマ2世は重病にかかり崩御してしまいます。王室典範によればモンクット親王(のちのラーマ4世)に王位継承権がありましたが、モンクットは僧侶でであり、学問に没頭していました。一方でタップは多くの公官庁での勤務を経験しており、ラーマ2世の晩年には事実上、王務を代行していました。このことから王位継承に関して王宮内で意見が分かれましたが、投票が行われタップが王位を継承することとなります。
即位に際して、ラーマ3世はそれまでラーマ1世を「最初の治世様」、ラーマ2世を「中期の治世様」と呼んでいたのを廃止し、それぞれに「プッタヨートファーチュラーローク」、「プッタルートラーナパーライ」という諡号を贈りました。これはラーマ3世が「最後の治世様」と呼ばれるおそれがあったためです。
また、即位の後に与えられた儀式的な名前は以下の通りです。ソムデットプラボーロマラーチャーティラートラーマーティボーディー・シーシントーンボーロママハーチャックラパッディラーチャーティボーディン・トーラニンタラーティラート・ラッタナーカーサパーソックラウォン・オンパラマーティベート・トリープーワネートラウォーラナーヨック・ディロッカラッタナラーチャチャートアーチャーワサイ・サムッタイカローモン・サコンチャックラワーラーティメン・スリイェンタラーティボーディン・ハリハリンタラーターダーティボーディー・シースウィブーン・クンアッカニット・リッティラーメースワラマハン・ボーロマタンミカラーティラート・デーチョーチャイ・プロムテーパーディテープナルボーディー・プーミントーンパラマティベート・ロークチェータウィスット・ラッタナモンクットプラテーサカター・マハープッターンクーン・ボーロマボーピット・プラプッタチャオユーフワ
27年間の即位の間、ラーマ2世は対中貿易で莫大な利益を収めました。ラーマ2世はこの利益を赤い袋に入れ、寝所に保管しました。このお金は「赤袋の金」とよばれ、ラーマ2世は「外国から攻撃され領土を失った場合、これで買い戻す」としてこの赤袋を大切にしました。
一方でラーマ3世は軍備の増強にも力を入れました。当時はビルマの コンバウン王朝 がイギリスの侵攻にあえいでいる最中であったため、この兵力を用いてベトナム勢力の進入をくい止めることは容易でした。同時にカンボジアの西部に侵攻しその領土をものにしています。またラオスのヴィエンチャン王国ではアヌウォン王がシャムに対して反旗を翻したのでこれを討伐したりもしています。
ラーマ3世は信心深い国王としても知られています。仏日には功徳のため貧困層の人民に食料を配給したり、動物を人間の手から解放したりしました(タイでよく行われる功徳)。また50以上の寺院を建立・修繕しました。
文人としても有名であり、ラーマ2世などと共にラーマ3世は『 クン・チャーン=クン・ペーン 』などの著作も行っています。 |
| |
 |
| |
| ■チャクリー王朝 ラーマ4世 |
| |
| 本名 チョームクラオ王 。幼名をモンクットと言うため、外国ではモンクット王が名前としてよく使われます。ただし、ラーマ6世の本名にもモンクットと言う語が登場するため注意を要します。元々は兄のラーマ3世よりも彼の方に王位継承権がありましたが、学業専念のために兄に王位を譲り、学問を続けました。即位までの27年間は寺に属し、経文の言語であるパーリ語 、サンスクリット語をマスターしました。その中でタイの仏教のあり方に疑問を感じてもいました。 |
|
|
| |
その後、キリスト教宣教師の手を借りて、英語 、ラテン語を学び、ルネサンスを通じて教義が合理化されたキリスト教にふれ、新時代の宗教は合理化されたものでなければならないと感じ、俗信を排除した仏教を建てました。このとき建てられた革新派の仏教集団を タマユットニカーイと言います。ラームカムヘーン大王碑文を発見した人でもあります。
即位後は、西洋との関係を重視し、イギリスからアンナ・レオノーウェンズ女史(Mrs. Anna Leonowens)を家庭教師に招き入れ、西洋の教育を子弟に行いました。このときのことは『 アンナとシャム王モンクット 』に書かれていますが、アンナに虚偽の癖があったため、信用しない方がよいとも言われています。この話は後に『王様と私』で劇作化、『アンナと王様』で映画化されましたが、いずれもタイでは上映が禁止されています。
西洋と自由貿易を開始し、米を輸出するようになりました。このためタイの中央平原部に運河が多く建設され、米の増産がはかられました。今でも米はタイの大きな輸出品目です。外国人の便宜を図るため、ニューロードを建設したりもしました。この王は62人もの子を残したと言われています。
当時、ルーシーダットンの壁画も描かれました。ソンクラー県のソンクラー市にあるワット・マチマワートには現在でも40ポーズのルーシーダットンの壁画が存在しています。 |
|
 |
| |
| ■チャクリー王朝 ラーマ5世 |
|
| ラーマ5世 (Rama V、1853年 9月20日 - 1910年 10月23日 )は本名を チュラチョームクラオ王 といいます。即位するとすぐに欧米に視察旅行をし、タイの立ち後れを実感。チャクリー改革と呼ばれる数々の改革を行いました。幼名をチュラローンコーンと言うため、外国では チュラーロンコーン大王 (King Chulalongkorn the Great)が名前としてよく使われます。タイ三大王のうちの一人で、今でも国民から人気が高く、肖像画が首飾りやポスターになったり、像が仏壇に置かれたりしています。1999年にはアメリカの『タイム』誌で、「今世紀もっとも影響力のあったアジアの20人」の1人に タイ人 から唯一選ばれています。 |
|
|
|
彼は以下のように大きな功績を残しました。まず、公然と行われていた奴隷売買を長年かけて廃止しました。アナンタサマーコム宮殿 にも奴隷解放の絵が残っています。 そして各地の王を廃止し、中央集権国家を作り上げました。他にも、官僚制を導入し行政を効率化したこと、議会制度の前身となる国政協議会と枢密院を設置したこと、学校教育を開始したこと、ラーチャダムヌン道路とその周辺を整備しバンコクからナコーンラーチャシーマーまで列車を通したこと、電話業務を開始したことなど、多くの偉業を成し遂げました。
そのころ、 ミャンマー (ビルマ)とマレーシアはイギリスに占領され、ベトナムがフランスに占領されていました。タイも狙われていましたが、チュラーロンコーンはイギリスにマレー半島の一部を割譲し、フランスにはラオスとカンボジアを割譲する事でこれを防ぎました。イギリス とフランスにしてみれば緩衝地帯としてタイを残しておきたかったと言うことと、チュラーロンコーンによってある程度近代化されていたのであからさまに占領できなかったという理由があるようです。
多妻多子でも有名です。チュラーロンコーンは正妻・副妻に異母の姉と妹を持ち、側室を入れた妻の数は160人以上、子供の数は77人と歴代最高だったため、ワット・プラケーオに併設された宮殿だけでは事足りず、ドゥシットに宮殿を造ったようです。これはドゥシット宮殿と呼ばれていますが、現在でも、ドゥシット公園動物園、ドゥシット公園師範学校、ウィマーンメーク宮殿、タイ王国国会議事堂、アナンタサマーコム宮殿、チットラーダー宮殿などに、その一部を見ることができます。
また、ラーマ5世は、ヤシの葉に書かれた古い医学書にも興味を持たれ、クメール語やパーリ語で書かれた医学書をタイ語に翻訳させたり、1895年国の医学書を印刷するなど、タイの伝統医学にも貢献しました。この医学書は後に改定され、医学文献とマッサージに関する知識が集められ、「タムラ・パサード・ソンクロ・チャバップ・ルアン」として現存しています。 |
|
 |
|
| ■チャクリー王朝 ラーマ6世 |
|
| ラーマ6世 (Rama VI、 1880年 1月1日 ? 1925年 11月26日 )は、幼名がワチラーウットというので外国では ワチラーウット王 (King Vajiravudh)とも言われています。タイの王朝史上、初めて海外留学をした王で、イギリスに滞在していました。帰国後は陸軍大将を勤め、1910年 に即位すると、ラーマ5世の始めたチャクリー改革 を押し進め、多くの改革を行いました。 義務教育制度の導入、発電所、水道施設、ドーンムアン空港、プット大橋の整備、現国旗の三色旗の採用、仏暦の採用、タイ赤十字社の設置、多妻制の廃止のほか、姓氏法を制定し国民に姓を持たせました。 |
|
|
|
 |
|
| ■チャクリー王朝 ラーマ7世 |
|
ラーマ7世 は、タイで最後の絶対君主で最初の立憲君主。本名はポッククラオ王。幼名が プラチャーティポックサックディデート というのでその一部を取って外国では プラチャーティポック王 とも言われています。
プラチャーティポックはバンコクの王宮で、ラーマ5世とパッチャリン妃の間に生まれました。 イギリスのイートン・カレッジ、ウールウィッチ士官学校、フランスのEcole Superieure de Guerreで学び、1924年の帰国後は短期間ながら軍人として働いていました。このときに軍人であったことをプラチャーティポックは王になった後も誇りにしていたようです。 |
|
|
|
本来であれば王になる予定ではありませんでしたが、ラーマ6世に成人した子供がいなかったため、ラーマ6世が崩御すると異母弟であった彼が急遽王位に就くことになりました。予期せぬ即位で、ラーマ6世が持っていた様な政治的基盤を築く暇がなかったため、政治的基盤が薄く、ラーマ7世は旧勢力の王族と、官僚の間で苦悶することとなりました。
ラーマ7世はラーマ6世時代に抱え込んだ負債の処理に即位後すぐに直面しました。この事態の打開を計るため5人からなる最高顧問会議を開き、全力で問題を解決しようとしましたが、アメリカが世界恐慌に見まわれたため、悪化していた国家財政がどん底まで悪化しました。そこで、王室費用を900万バーツから最終的に300万バーツに切りつめる「合理化」を行ったことでも有名です。ラーマ7世はついでに官僚の人事も「合理化」したため官僚、なかんずく民主的な雰囲気の中で教育されたフランス留学組官僚の怒りを買いました。この合理化に対する危機感は、後に人民党を生み出しました。
ラーマ7世は1931年眼病手術のためアメリカを訪れた時から、議会制導入を考えるようになりました。そのための憲法草案を作成し、いざ発表する段階になると、最高顧問会議のメンバーを中心とする王族の猛烈な反対に遭い断念しました。これに業を煮やしたパホン大佐、 ピブーンソンクラーム、 プリーディー・パノムヨン率いる人民党が、ラーマ7世がフワヒンへ療養に出かけている最中に立憲革命を起こし、 1932年ラーマ7世に憲法を発布させました。これにより、ラーマ5世以来続いた絶対王政に終止符が打たれたのです。
しかし、新政府は王政を廃止せず、代わりに国王の承認を権力のよりどころとする立憲君主制を導入したため、ラーマ7世は翌年、目の病気を理由にイギリスへ逃亡しました。国王の承認をよりどころにしていた新政府は、国王の承認を取り付けるためイギリスまで行かねばならず、事務の円滑な処理が出来なかったので、ラーマ7世にタイへ戻るように頼みましたが、ラーマ7世は拒否し続けました。その後、いつまで経っても民主制に移行しようとしないパホン政権に抗議するためにラーマ7世は1935年自らの意志で退位しました。そのままイギリスで不遇なまま過ごしましたが、1941年に死亡しました。遺骨は1949年にタイへ帰還しました。 |
|
 |
|
| ■チャクリー王朝 ラーマ8世 |
|
ラーマ8世 (Rama VIII、 1925年 9月20日 - 1946年 6月9日 )は本名を アーナンタ・マヒドン王 という。外国では、アーナンタ王 、マヒドン王とも呼ばれています。ラーマ5世の孫で、ラーマ7世の甥に当たる人物。 1925年 (タイ仏暦2468年)ドイツのハイデルベルクで生まれました。
1928年 (タイ仏暦2471年)年に初めてタイに帰ってきましたが、翌年に父親が亡くなると、兄弟三人でスイスのローザンヌで修学しました。1934年(同2477年)ラーマ7世が退位するとタイの国会の決定で即位しましたが、すぐにスイスに帰り学業を続けました。1945年 (同2488年)に学業を終え帰国しましたが、翌年には「事故」で崩御しました。 |
|
|
|
| ボーロマピマーン宮殿で銃声がしたので駆けつけてみると、ラーマ8世は死んでいた、といわれています。そのまま銃の暴発事故で片づけられそうになったが、警察が検死結果を元に他殺説を示唆しました。ラーマ8世死亡事件捜査本部が設置されたものの結局それ以上の捜査は続けられず、責任をとって内閣は総辞職し、数人の王室関係者が処刑されました。後にこの事件に関してラーマ9世の協力の下で調査した小説家でジャーナリストでもあるウィリアム・スティーブンソンはその著作・ 「革命の王 (原題: The Revolutionary King )」で証拠を提示し、旧日本軍の参謀・辻政信による犯行の可能性が高いと示唆しました。しかしながら辻政信の記録、『潜行三千里』によれば辻は1945年にタイを脱出しており、1946年6月9日は中国にいたことから、わざわざバンコクまで戻りラーマ8世を暗殺するのは不自然であるともいえます。 真相は未だもって不明。不敬罪に抵触する可能性があるので、タイではこの問題に深入りすることが今なおタブーとなっています。 |
|
 |
|
| ■チャクリー王朝 ラーマ9世 |
|
ラーマ9世は、「プミポン国王」(「類まれなる強い土地の力」を意味する)とも呼ばれ国民から広く親しまれていました。
1927年( タイ仏暦 2470年)12月5日、アメリカのマサチューセッツ州 ケンブリッジに生まれました。ラーマ5世の69番目の子息、ソンクラーナカリン親王を父に持つ人物。学業はスイス のローザンヌ大学で修めました。 学業中にいったん休学し、第二次世界大戦終結後の1945年(タイ仏暦2488年)にタイへ帰国しますが、翌年の1946年6月9日に兄ラーマ8世アーナンタが怪死したために、兄王の死の12時間後にタイ国王に即位。その後すぐにローザンヌ大学へ復帰し、1952年(タイ仏暦2495年)に帰国しました。 |
|
|
|
同年、フランス滞在中に出会った同じく王族のモム・ラーチャ・ウォン・シリキット・キッティヤーコーン(シリキット)と結婚します。その後1956年(タイ仏暦2499年)にはタイの仏教の伝統に基づき、仏門に入り一時的に俗世間を離れ、還俗(再び俗世に復帰)しました。その後一男三女をもうけました。
官僚、軍部が着実に政治的力を付けた上に、第二次世界大戦後の冷戦下において共産主義化の波を受け、ベトナムやカンボジアなど 東南アジアの周辺諸国のみならず国内が混乱するかに見えたときも、事態の収拾に見事なまでの政治的手腕を見せました。
1992年に発生したクーデター未遂事件「5月の惨劇事件」では、軍を背景にするスチンダー 首相と民主化運動グループの民間人指導者、チャムローンを玉座の前に等しく正座させ、説得のみで騒乱を一夜にして沈静化させたという逸話があり、「人間性が高く慈悲深い人物である」という、タイ国王が伝統的に行うべきとされるノーブレス・オブリージュに一層の真実味を与えた一方で、プーミポン国王自身の政治的な成熟を見せつけ、権力のバランサーとしての側面を強調するものとなりました。
2003年に隣国カンボジアとの間で小競り合いになり、扇動されたタイ国民が在タイカンボジア大使館に押し寄せた際には、「悪党の言葉に惑わされてはならぬ」と明快無比な表現で帰宅させました。 2006年4月には野党が立候補をボイコットした下院総選挙を「民主主義的ではない」との理由でやり直しを示唆し、憲法裁判所が国王の意向を受けてやり直しを命じました。
2006年6月には即位60周年を祝う祝賀行事が国を挙げて執り行われ、日本やベルギー 、サウジアラビアやオランダなど世界25ヶ国の君主制を採る国々から王族、皇族も参列し国王の即位60年を祝いました。なお、日本からは今上天皇も参列しました。
「ロイヤル・プロジェクト」と呼ばれる農業をはじめとする地方経済の活性化プログラムを自ら指導する他、自ら土地改革運動のために王室の所有地を提供したり、農村開発や干ばつ対策の人工雨等の各種王室プロジェクトを推進しています。また、王妃とともに地方視察も非常に精力的に行い、確実にタイ国民の尊敬と信頼を勝ち得ました。毎年誕生日前になると全国各地に肖像画が飾られ、国王の色とされる黄色いシャツを着用した市民で埋め尽くされるほどです。
プミポン国王がタイで広く非常に尊敬され支持されていたのは、学校教育で行われているプミポン国王に対する崇拝や不敬罪といった強制的なものによるものではなく、上記のような様々な功績が評価され、国民の間に自発的に尊敬の念がおきているからと国内外より評価されています。 NHKラジオ深夜便の海外レポートコーナーなどで紹介する際も、必ず「(タイ国民が)敬愛するプミポン国王」という表現を使っています。こうしたプミポン国王自身の人格性の高さが、タイの政治的安定を維持していました。
歴史的にタイの王室は日本の皇室と縁が深く、国王自身も1963年5月に初来日し、当時の 皇居仮宮殿で昭和天皇と会談を行っている他、今上天皇と皇后とも数度に渡り会談を行っています。また、タイを公式、非公式で訪れることの多い秋篠宮文仁親王を「我が子と同様」であるとして懇意にしています。なお、日本製の製品を日常に数多く使用することでも知られ、一時期王宮内の移動用にホンダ・アコードを3台に渡り使用していた他、キヤノンの一眼レフカメラを長年愛用していることも有名でした。
2009年9月19日、発熱などのため再びシリラート病院に入院、2012年5月に一時退院し、アユタヤ県の洪水対策工事の視察に出かけ健在をアピールしたが、その後は高齢のため普段はフワヒンにあるクライカンウォン宮殿に居し、公務の数を減らしていました。
2016年6月9日は在位70年を迎え、存命中の最も在位年数の長い君主となりました。在位70年を祝う記念行事が執り行われましたたが、国王本人は入院中でした。入院している病院の周りには、タイでは健康と長寿を意味する色であるピンク色の服を着た人々が集まりを手を合わせ、肖像を掲げ、国王の平癒を祈っていました。 2016年10月9日夜 タイ政府は、プミポン国王の容態が不安定だという声明を発表。タイ全国民に緊張がはしった。その当時は、プミポン国王の病院の前には、国王を心配する国民で埋め尽くされました。 惜しくも2016年10月13日この世を去ってしましました。
特記すべきは、ラーマ9世のタイ古式マッサージに関することです。ラーマ9世がいなければ、今日のようにタイ古式マッサージが世界に広まることはなかったでしょう。現在でも、バンコクにあるワットポー寺院がタイ古式マッサージの総本山として名高いのか?それは、ワットポーが皇室系のお寺だからです。ワットポーは、1788年、ラーマ1世によって建 てられたバンコク最古の寺院で、ラーマ1世は、当時、寺の医者や、民間の医者を集めて、タイハーブやタイ伝医学の知識を集め、壁に刻ませたことでも有名なのです。また、ラーマ1世はワットポーの境内にルーシーダットン像を土で作らせ金箔を貼り付けたが、このルーシーダットン像は現存していません。当時、いくつのルーシーダットン像が作られたのかは不明。このあたりが、どうも総本山という表現になっていったようです。特に全長46m、高さ15mの巨大な腕枕して寝転がってる仏像が有名でタイ旅行では定番の観光名所にもなっていますが、境内にはタイ国王の墓がある皇室系の由緒正しいお寺なのです。
ワット・ポー伝統医学学校が寺院内に設立されたのが、1957年。しかし、タイマッサージを教えるスクールとしての環境は整っていなかったようです。4年後の1961年、プミポン国王(ラマ9世)がワットポーを訪問した際に、「タイマッサージは教えていないのか?」という一声から、ワットポーでタイマッサージを広く一般の人々に教えるようになりました。ワットポータイ伝統医学校の経営はもともと赤字続きで、当時はタイマッサージの風俗的なイメージをぬぐいきれなかったために、あまり生徒は集まらなかったようです。いずれにしても、タイ伝統医学的な厳格なタイマッサージから脱皮して、タイマッサージを単純で、平易で、覚え易くしたワットポータイマッサージスクールの試みが、バカ受けして、第1次タイマッサージブームを迎えることになるわけです。プミポン国王(ラマ9世)のお言葉がなければ、今日のようにタイマッサージが世界的にポピュラーな存在になることはなかったでしょう。 |
| |
 |
| |
| ■チャクリー王朝 ラーマ10世 |
| |
1952年、タイ国王・ラーマ9世とシリキット王妃の長男(第2子)として王宮で生まれました。幼少期はバンコクで学んだが、1966年からイギリスへ渡り、キングスミード校およびミルフォード校(サマーセット)で学びました。1970年にはオーストラリアに渡り、キングス校(シドニー)で陸軍予科課程を修めました。1972年には皇太子としての名称、ソムデットプラボーロマオーラサーティラートチャオファー・マハーワチラーロンコーン・サヤームマクットラーチャクマーン(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร)を父王より付与され、王位継承権を得ました。
2016年10月13日、父であるラーマ9世の崩御を受け、プラユット・チャンオチャ首相が「ワチラーロンコーンが新国王に即位する」ことを発表しました。現在タイ国王はラーマ10世です。
|
| |
| |
| |